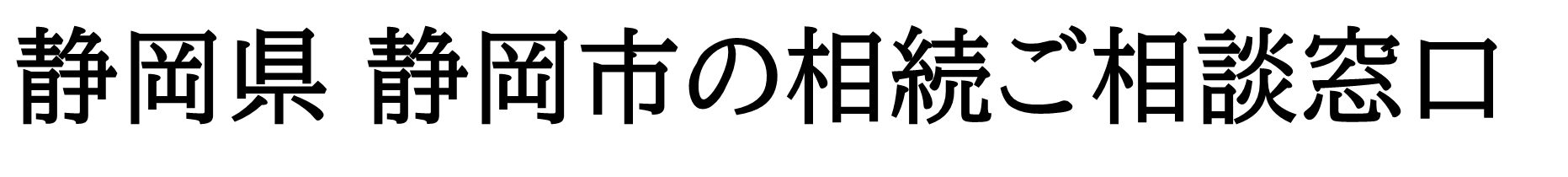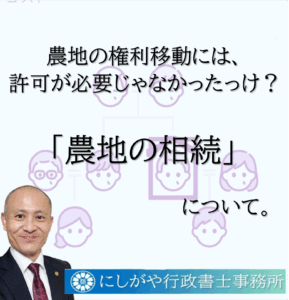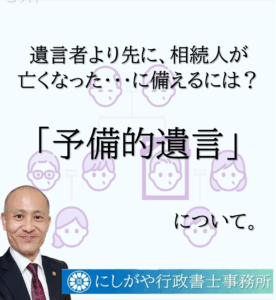Vol.45|「相続」|農地の相続(後編)|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
今回のテーマはこちら
↓ ↓ ↓
農地の相続について(後編)
農地の相続は、通常の宅地等の相続と違って、手続きが複雑化することがあります。
今回は、前回に引き続いて「農地の相続(:後編)」について概説します。
・ ・ ・ ・ ・
農地を、引き続き農業をするつもりで相続する場合は、手続きはそれほど複雑ではありません。要件を満たせば、税制上の優遇措置(相続税の納税猶予)を受けられることもあります。
問題は、
・農業を継続しない場合
・農地の相続を放棄する場合
です。
農業を継続できない場合でも、農地として相続したその土地の管理をしていかなければなりません。土地が荒れてしまえば、近隣にも迷惑がかかります。
相続人が農業をしていない場合や遠方で生活していた場合は、相続するメリットが見出せません。
そういった場合には、「賃貸」や「売却」・「他の用途に転用(して活用等)」することなどが選択肢として考えられます。
ただし、どの場合でも勝手には出来ず、農地法の規定や農業委員会の存在を無視して進めることは出来ません。
「賃貸」、つまり農地を貸し出す場合も、原則農地法上の許可が必要になります。借り手を探すのが自分では難しい場合は、農業委員会やJAに相談する事が出来ます。
「売却」を検討する場合、一旦相続登記をして、その上で売却をするという手順になります。ただ、売却の相手も誰でも良い訳ではなく、一定の制限があります。
売却以外に、駐車場にしたり、賃貸する目的で宅地化したり「他の用途に転用」することも選択肢に上がってくるでしょう。
ただしこの場合も、農地法上の届出や許可が必要となり、また農地が都市計画上のどのエリアに在るのかや、農地の種別によっては転用が難しい場合もあります。
売却にしても転用にしても、幾つもの確認や調査が必要な事もあるので、農地を相続する場合には行政書士などの専門家へ相談した方が、手続きをする上では安心出来ます。
一方、農業をしない、相続しても維持管理が大変な場合に、「相続をしない=相続放棄」することが選択肢に入ってくると思われます。
ただしこの場合には、農地だけ相続を放棄する、といったことは出来なくて、放棄するなら相続分全てについて放棄しなければならなくなります。
また、相続放棄する場合には、家庭裁判所に申述しなければなりませんが、期限が定められており、相続の開始を知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。
以上のように、農地の相続の場面で、引き続き農業を継続する以外の場合には、通常の相続手続きに加えて、農地法上の手続きが必要になり、全体として複雑になることがあります。
どうすべきか、どうしたいかの判断も含め、専門家への相談が重要だと考えます。
・ ・ ・ ・ ・ ・
今回は、「農地の相続(:後編)」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
お問い合わせからの流れ
- 1.お問い合わせ
- お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームの場合は、折り返しご連絡致します。
- 2.ご面談
- 日時を決めて当事務所、又はお客様のご自宅等でご相談内容を詳しくお聞きします。ご面談時に必要な資料・書類等は予めお伝えした上で御用意いただきます。
- 3.お見積り
- お客様のご相談内容や状況に応じて、サポート内容とお見積り額をご提示致します。
- 4.業務委任契約・着手
- サポート内容やお見積りにご納得頂けましたら、業務委任契約を締結し、業務着手致します。受任後、途中経過やお客様のご協力が必要な場合も都度ご連絡致します。
※業務開始時に着手金(お見積り時ご説明)をお受けする場合がございます。
- 5.業務終了・作成書類等のお引渡し
- 受任した内容・お手続きが終了しましたら、そのご報告と共に作成書類等をお引渡し致します。
お問い合わせはこちら!
セミナー情報:テーマ「相続」と「お金」のはなし。
令和7年10月22日(水)に、藤枝市「ふじキャン」で、セミナーを開催する予定です。
詳細は下記記事をご確認下さい。
遺言書・相続に関するご相談は、静岡市清水区のにしがや行政書士事務所まで!