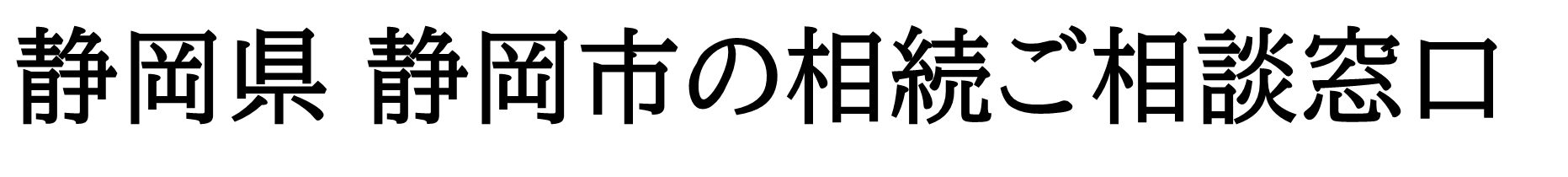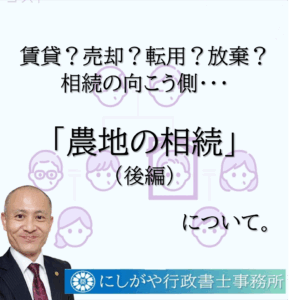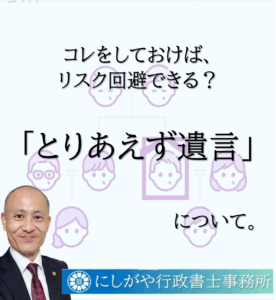Vol.46|「相続」|予備的遺言|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
今回のテーマはこちら
↓ ↓ ↓
遺言者より先に相続人が亡くなった…に備える「予備的遺言」
遺言書では、遺言者の有する財産について「〇〇に相続させる」などと記載します。
ところでもし、遺言者よりも、その指定した相続人が先に亡くなった場合にはどうなるのでしょうか。
この場合、例えば相続人が亡くなったのなら、その子供に自動的に代襲相続される・・・訳ではありません(そのような判例があります:最判平成23年2月22日)
指定していた相続人が先に亡くなっていた場合は、その相続分につき無効とされ、改めて相続人間での協議が必要となります。
こうなると、わざわざ遺言で財産の承継先を指定した意味が無くなってしまいますよね。
こういった事態になることを避けたい場合、どうしたら良いのでしょうか。
この問いに応えるのが、「予備的遺言」という方法です。
今回は、「予備的遺言」について概説します。
・ ・ ・ ・ ・
例えば、
・遺言者 A
・相続人 子B
・相続人 子Bの子C
という関係の中で、「遺言者Aは、その有する財産・・・を、Bに相続させる」と定めたとします。
そして、万が一BがAよりも先に亡くなった場合のことを想定して、「遺言者Aは、Aよりも先にBが死亡した場合、またはAとBが同時に死亡した場合は、Aの有する財産・・・を、Bの子である孫のCに相続させる」と定めておきます。
こうすることで、万が一遺言者Aよりも先に遺言者Bが亡くなった場合やAとBが同時に亡くなった場合に、財産の帰属先が無くなってしまう事を避けることが出来ます。
遺言者が高齢で、遺言者と年の近い配偶者などに〇〇を相続させる、といった場合、配偶者の方が先に亡くなることは十分考えられます。
なので、そういった場合の財産の受取手を決めておくことで、安心することができます。
※「遺言者と相続人が同時に死亡した場合」も、その相続人に相続させようとした部分が無効になってしまうので、「先に死亡した場合」と同じように定めておく必要があります。
この、相続させようと指定した相続人が万が一先に亡くなった場合に備えて、次に相続させる者を定めておくことを「予備的遺言」と言います。
なお、同一の公正証書で主たる遺言内容と予備的遺言内容を併せて記載する場合は、公正証書の作成手数料としては、主たる遺言内容にかかる財産額に対する手数料の算定となり、予備的遺言内容の部分については手数料はかかりません。
ただし、主たる遺言内容を記載した公正証書を作成して、後日追加的に予備的遺言の公正証書を作成する場合は、予備的遺言にかかる財産額に対する手数料がかかってきます。
この辺りは、日本公証人連合会HPにその記載があります。
・ ・ ・ ・ ・
今回は、「予備的遺言」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
お問い合わせからの流れ
- 1.お問い合わせ
- お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームの場合は、折り返しご連絡致します。
- 2.ご面談
- 日時を決めて当事務所、又はお客様のご自宅等でご相談内容を詳しくお聞きします。ご面談時に必要な資料・書類等は予めお伝えした上で御用意いただきます。
- 3.お見積り
- お客様のご相談内容や状況に応じて、サポート内容とお見積り額をご提示致します。
- 4.業務委任契約・着手
- サポート内容やお見積りにご納得頂けましたら、業務委任契約を締結し、業務着手致します。受任後、途中経過やお客様のご協力が必要な場合も都度ご連絡致します。
※業務開始時に着手金(お見積り時ご説明)をお受けする場合がございます。
- 5.業務終了・作成書類等のお引渡し
- 受任した内容・お手続きが終了しましたら、そのご報告と共に作成書類等をお引渡し致します。
お問い合わせはこちら!
セミナー情報:テーマ「相続」と「お金」のはなし。
令和7年10月22日(水)に、藤枝市「ふじキャン」で、セミナーを開催する予定です。
詳細は下記記事をご確認下さい。
遺言書・相続に関するご相談は、静岡市清水区のにしがや行政書士事務所まで!