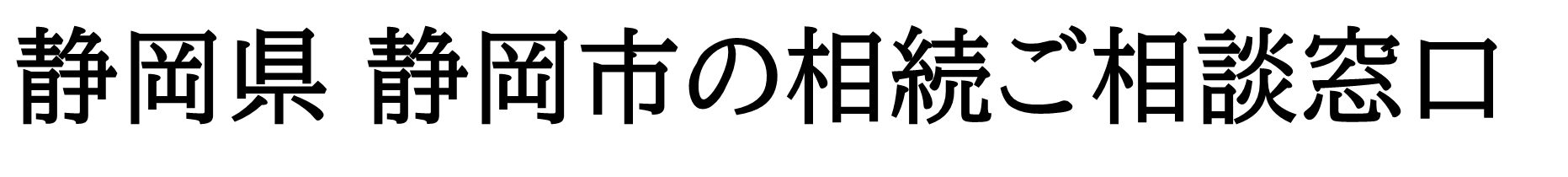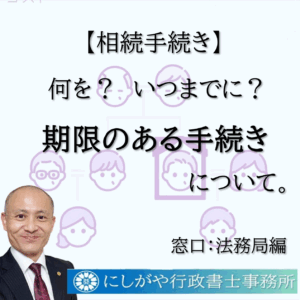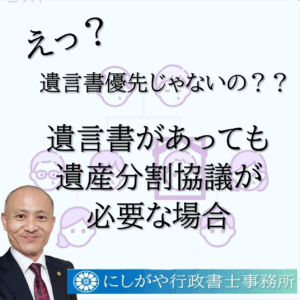Vol.12|「相続」|相続開始後(死亡後)の手続き期限別ガイド:家庭裁判所編|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
今回のテーマはこちら
↓ ↓ ↓
期限のある相続手続き|窓口:家庭裁判所編
人が死亡して相続が開始すると、様々な手続きをこなさなければなりません。
中には、期限が設けられている手続きもあります。
今回は「家庭裁判所」に対する手続です。
・ ・ ・ ・ ・
①相続放棄 自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヵ月以内に申述
②限定承認 自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヵ月以内に申述
①相続財産は、プラスの財産ばかりではありません。借金もマイナスの財産として相続財産に含まれます。
しかし、マイナスの財産がプラスの判断を上回る場合、「相続したくない」と考える相続人も居ると思います。
そういった場合は、「自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヵ月以内」に「家庭裁判所」に対し、「相続放棄の申述」をすることが出来ます。
この、家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、遺産分割協議の際に、他の相続人に遺産を譲りたい場合に辞退する相続放棄と違って、「初めから相続人では無かった」ことになる点が、大きなポイントです。
相続人ではないので、相続放棄した人が死んだ場合に、通常の相続人が死亡した場合に、その下の世代に相続が起こる「代襲相続」は発生しません。
遺産分割協議で辞退する事を指す相続放棄と、家庭裁判所に対してする相続放棄の手続きでは、その効果が異なるので注意が必要です。
②限定承認は、相続によって取得したプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐことを言います。
借金がある事が分かっていても、その総額が分からない場合などに利用される手続です。限定承認の手続きをすれば、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていても、相続人は損をしません。
限定承認は、「自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヵ月以内」に「家庭裁判所」に対し、「限定承認の申述」をします。
ポイントは、一部の相続人だけで手続きするのではなく、「共同相続人全員で」しなければならない点です。この際、相続放棄した者は、相続人ではなかったとみなされるので、それ以外の共同相続人で申述することになります。
・ ・ ・ ・ ・
以上のように、家庭裁判所に対する手続きには、期限のあるものがあります。
相続の方向性を検討する際に、期限を意識しなければ、意図しない結果を招くことも起こり得ますので、相続手続きについては、専門家に伴走してもらう事をおススメします。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
セミナー情報
下記記事で、今後のセミナー開催予定を紹介しています。
是非ご確認頂き、ご参加ください!