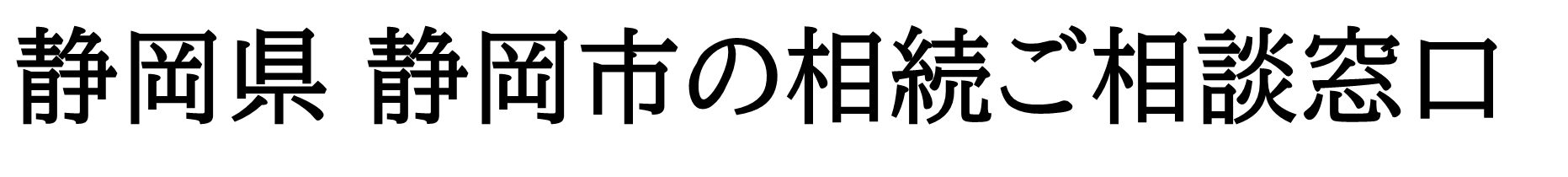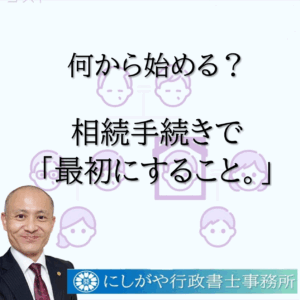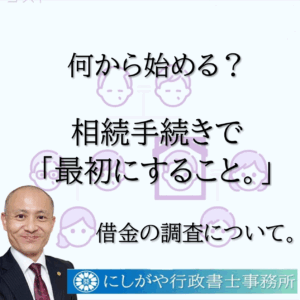Vol.17|「相続」|相続手続きで最初にすること「相続財産調査」について。|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
今回のテーマはこちら
↓ ↓ ↓
何から始める?相続手続きで「最初にすること」。「相続財産調査」。
相続と聞くと、遺産分割や相続税など、キーワードはよく知られていると思いますが、実際の手続きの中身や流れはどうなっているのでしょう。
今回は、前回に引き続き相続手続きで最初にすることの内、「相続財産調査」について概説します。
相続手続きを進める為には、相続人と相続財産を確定させなければなりません。
相続財産は、それが明らかにならなければ、遺産分割も、相続放棄の判断も、相続税の算出も出来ません。また、相続放棄は相続の開始を知った時から3ヵ月以内、相続税は10カ月以内の申告・納税をしなければならない等、期限のある手続きもあるので注意が必要です。
相続財産は、故人の財産の全て、つまりプラスの財産の他、マイナスの財産も調査します。
プラスの財産の例
・預貯金
・不動産
・自動車
・株式
マイナス財産の例
・借金
・住宅ローン等
・連帯保証人としての債務
・未払いの税金
上記は一例です。
以下、代表的な財産である預貯金・不動産それぞれの財産調査の方法について概説します。
・預貯金
預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関からのはがきなどを手掛かりに調査します。
金融機関名が分かれば、窓口にて残高証明書の発行手続きをすることで、死亡時残高や、定期預金の有無や金額が分かります。
手続きは、相続人1人でもできます(但し解約の場合は相続人全員の同意が必要です)。
手続き書類は、亡くなった人の戸籍謄本、請求する人(相続人)の戸籍謄本、請求する人(相続人)の実印・印鑑証明書、請求する人(相続人)の本人確認書類、発行手数料等です。
尚、どこの金融機関を利用しているかが全く分からない場合は調査が困難になりますが、せめて金融機関名だけでも分かれば、全店照会をして、支店や口座を判明させることが出来ます。
また、亡くなった方のパソコンの閲覧履歴・メール履歴等からネットバンクの利用が分かる場合もあります。
・不動産
不動産の調査は、売買契約書や登記簿謄本の有無の確認の他、名寄帳の請求、郵送されてくる固定資産税納税通知書等より調査します。
名寄帳は、不動産が所在している市区町村に請求できる、所有する不動産の一覧表のようなものです。
また、固定資産税納税通知書には、不動産の所有状況が分かる固定資産税課税明細書が同封されています。
これらより、調査対象の不動産の所在や家屋番号・地番を確認し、登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で取得し、所有者の確認をします。
名寄帳請求の必要書類は、亡くなった人の戸籍謄本、請求する人(相続人)の戸籍謄本、請求する人(相続人)の本人確認書類、発行手数料等です。市区町村の固定資産税課で請求できます。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、所定の交付申請書に記入し、発行手数料(印紙代)を収めることで取得できます。
以上、相続財産調査の方法について概説しました。あくまで「概説」なので大まかであったり、他の調査方法や調査場所、気を付けるべき点などありますが、それらについてはまた別の機会のテーマにします。
借金の調査方法についても、今後説明したいと思います。
相続人調査、相続財産調査は、自分で進めるには骨が折れる作業なので、専門家のサポートを受けることをおススメします。自分で進めるよりも、手間や労力や時間を大幅に省けます。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
セミナー情報
下記記事で、今後のセミナー開催予定を紹介しています。
是非ご確認頂き、ご参加ください!